ツイスト・ドリル加工の基本
今回は、私が長年携わってまいりました金属加工の中から、特に「穴あけ加工」、それも身近な「ツイストドリル」を使った加工の基本について、少しお話しさせていただこうかと思います。
一見単純に見えるドリルでの穴あけですが、実は基本的なことがたくさん詰まっている奥深い作業なのです。
ドリル加工は基本が詰まっている
私自身、普段の仕事でごく一般的な、あの黒っぽい「ツイストドリル」をよく使っています。シンプルな丸い穴をあけるには、昔からあるこのドリルが一番手になじんでいるからです。もちろん、同じ穴をたくさんあけたり、大量の品物(ワークと呼びます)を加工したりする必要がある時には、OSGさんのEXゴールドドリルやNACHIさんのAG-ESSドリルといった、少し性能の良いハイスドリルを使うこともあります。超硬ドリルという、もっと速く削れるドリルもあるのですが、私の場合は少量生産が多いものですから、そこまでには至っていません。おそらく、超硬ドリルを使えば驚くほど加工時間は短くなるのでしょうね。
それでも、やはり一番出番が多いのは、このツイストドリルです。なぜかというと、使い込んで切れが悪くなった時に、自分で研ぎ直してまた使えるからです。
ドリルを機械に取り付けて、くるくる回しながら材料に押し付けてやれば、確かに穴は簡単にあきます。しかし、「切削条件」、つまりドリルを回す速さ(回転数)や、材料に切り込んでいく速さ(送り)の設定を間違えてしまうと、思った以上に時間がかかってしまったり、ドリルがすぐに傷んでしまって何度も研ぎ直す必要が出てきたりします。
古いタイプのボール盤や、少し大きなラジアルボール盤といった機械を使う時は、機械の前面や側面に書いてある目安を見て回転数を決め、あとはハンドルの感触で「適当に」押し付けて穴をあける、ということもできます。ですが、最近の「NC工作機」(コンピューターで動きを制御する機械のことです)を使う場合は、少なくとも「回転数」と「送り」の知識がどうしても必要になります。
ところが、この一般的な黒いツイストドリルについて、「この材料には、この回転数でこの送りが良いですよ」というような、はっきりとした切削条件のデータを目にする機会は、意外と少ないように感じます。ですから、特にこれから加工を始めようという方にとっては、「どう設定すればいいのだろうか…」と不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでこれからお話しする内容は、あくまでも「加工を始めるための、最初の取っ掛かり」として見ていただければ幸いです。実際に加工を進めていく中で、ドリルの様子や切りくず(削りかす)の形、音などを見ながら、随時条件を変えていくことを強くお勧めします。基本はもちろん大切ですが、最終的には工具の寿命(どれだけ長く使えるか)、機械や材料のしっかり具合(剛性)、そして切削液(切削油のことです。摩擦や熱を抑えたり、切りくずを流したりします)を使うかどうか、その性能などを総合的に考えて調整していく必要があるからです。
回転数はどうして決めるか
私もこの世界に入って長いですが、手動のボール盤程度であれば、これまでの経験だけでだいたいの回転数は判断できます。加工中に聞こえる音や、出てくる切りくずの色などを頼りに、「もう少し速く回そうかな」「いや、少し遅くしよう」と調整していくのです。最初は材料に恐る恐る穴をあけていくのですが、慣れてくると自然と回転を上げて、ハンドルを強めに押せるようになってきます。
これがNCボール盤やマシニングセンターといったコンピューター制御の機械になってくると、こちらで回転数と送りを数字で決めて機械に教えてやる必要があります。機械によっては、ある程度の条件を自動で決めてくれる機能がついていることもありますが、自分で決めなくてはいけない場面もたくさんあります。
回転数を考える上で、どうしても知っておくと後々便利なのが「切削速度 [m/min]」という考え方です。これは、ドリルの一番外側の刃先が、1分間に材料をどれだけの長さ(メートル)で削り進むか、という速さを表しています。この切削速度を基準に考えると、ドリルの直径が変わっても、材料に応じた適切な回転数を計算で求めやすくなるのです。
計算式は以下のようになります。
ここで「rpm」というのは、ドリルが1分間に何回転するか、という単位です。「π(パイ)」は円周率の約3.14のことですね。
たとえば、一般的な鉄(SSやS45Cなど)を加工する場合は、切削速度を「20 m/min」あたりで計算してみると良い出発点になります。アルミ材料の場合は、もっと速く削れるので「40 m/min」で計算して出すことが多いですね。ただし、細いドリルを使う場合は、計算上はもっと速い回転数が必要になりますが、私の機械の上限で制限されてしまうこともよくあります。
送りはどうして決めるか
さて、回転数の次は「送り」です。送りとは、ドリルが材料に切り込んでいく速さのことです。単位は通常 [mm/min] で表され、「ドリルが1分間に材料へどれだけ深く入っていくか」を示します。
ツイストドリルには、先端に主に二つの刃がついていますが、「刃一つあたりでどれだけ材料が進むか」という考え方(一刃送りと呼びます)は、私はあまり意識していません。
経験的な数値にはなりますが、一般的な鉄(SS、S45Cなど)を削る場合、「一回転当たりの送り」を「ドリル径の1%」から、状況によっては「最大2%」程度を目安にしておけば、最初の条件としては良いのではないかと思います。ここで言う「一回転当たりの送り [mm/rev]」とは、ドリルが1回転する間に、材料にどれだけ食い込んでいくか、という量のことです。最初はこの目安で始めてみて、あとは実際の加工で出てくる切りくずの形や、ドリルにかかる負担などを観察しながら、ご自身の機械や材料、ドリルにとって一番良い値を見つけていくのが一番です。
少し太めの、13mmを超えるようなドリルを使う場合は、いきなり目的の太さのドリルで穴をあけるのではなく、それよりも細いドリルで一度「下穴」をあけておくことがあります。そうすることで、太いドリルにかかる負担を減らせるので、一回転当たりの送りを2%よりも大きくすることも可能になります。
私の場合は、5mm未満の細いドリルでは「ドリル径の2%」、5mmから13mmくらいのドリルでは「0.1mm/rev」を最初の送りとすることが多いです。そして13mmを超えるドリルでは、状況に応じて下穴をあけてから、最低でも「0.2mm/rev」の送りを設定することが多いですね。たくさんの穴を連続であけるような時は、加工の様子を見ながら、少しでも時間を短縮するために条件を上げていくこともあります。
送り [mm/min] は、先ほど決めた回転数と、この一回転当たりの送りを使って計算できます。
送り[mm/min] = 回転数[rpm] × 一回転当たりの送り[mm/rev]
ここで少しややこしいのですが、「送り」にはいくつか考え方があります。
- 回転一刃当たりの送り [mm/(rpm・tooth)]:刃一つあたり、1回転あたりに進む量
- 一回転当たりの送り [mm/rev]:1回転あたりに進む量
- 一分間当たりの送り [mm/min]:1分間あたりに進む量
といった具合です。話の中でどの送りのことを言っているのか、混同しないように注意が必要ですね。
ステンレス材の場合
皆さんもご存知の通り、ステンレスは粘り強く、穴あけが少し難しい材料です。ドリルが滑ってしまったり、「キーキー」と嫌な音が出たりすることもよくあります。
もしステンレス材の穴あけがうまくいかない場合は、先ほどの一般的な鉄の場合の「切削速度を半分」にしてみて、その代わり「1回転当たりの送りを二倍」にしてみる、という方法を試してみてください。これは、切削速度を遅くして、材料が硬くなりにくくしつつ、硬くなり始める前に一気に削り取ってしまおう、という考え方に基づいています。ステンレスは「加工硬化」といって、削っているうちにその場所がどんどん硬くなってしまう性質が強いのです。
具体的な数字としては、切削速度を「10~12 m/min」あたりで試してみると良いでしょう。もし「キーキー」と金属がこすれるような嫌な音がするようでしたら、一旦切削速度を「7 m/min」くらいまで落としてみてください。
送りについては、ドリル径が5mm以上の場合でしたら、「0.1mm/rev」以上を設定し、可能であれば「0.2mm/rev」あたりを設定してみるのがおすすめです。
SCMなどの焼きが入り易い材質の場合
SCM材のように、熱を持ちやすく「焼きが入り易い」材料を加工する場合も、少し注意が必要です。焼きが入るというのは、摩擦などの熱によって、削っている材料やドリルの先端が急激に硬くなってしまう現象のことです。一度焼きが入ってしまうと、ドリルは急激に切れなくなり、すぐに使えなくなってしまいます。
このような材料の切削速度は、一般的な鉄(SS、S45Cなど)と同等か、少し遅めの「2/3程度」を目安に見ています。具体的には「12~15 m/min」あたりでしょうか。もし材料が熱処理(調質といいます)をして硬さが調整されている場合は、さらに遅く「10 m/min」にする場合もたまにあります。
この手の材料で送りを少なめに設定しすぎると、ドリルの先端と材料がこすれる時間が長くなり、摩擦熱で材料の方に焼きが入ってしまうことがあります。そうなると、ドリルはあっという間にダメになってしまいます。もし、出てくる切りくずや、ドリルの先端が黒っぽく変色している場合は、熱を持ちすぎている証拠ですので、切削速度を下げる必要があります。
送りについては、ドリル径5mm以上であれば最低でも「0.1mm/rev~0.15mm/rev」は必要です。13mmを超えるような太いドリルで下穴をあけていない場合は、さらにドリルの負担が大きくなりますので、最低でも「0.2mm/rev」の送りが必要だと考えています。
そして、この手の材料では、「切削油」または「切削液」はほぼ必須と考えた方が良いでしょう。油や液を使うことで、摩擦熱を抑え、焼き付きを防ぎ、切りくずをスムーズに排出してくれるからです。
さて、今回はツイストドリルを使った穴あけ加工の、基本的な切削条件の考え方についてお話しさせていただきました。
繰り返しになりますが、ここでご紹介した数値は、あくまで「最初のスタートライン」です。実際の加工では、材料の種類や硬さ、ドリルの状態、機械の特性、使う切削油の種類など、様々な要因によって最適な条件は変わってきます。
まずはこれらの数値を参考に、ご自身の目で、耳で、そして手の感触で加工の様子を確かめながら、少しずつ条件を調整してみてください。そうやって、ご自身の「最適解」を見つけていくことが、きっと加工の腕を上げる一番の近道になるはずです。
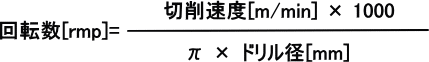

コメント
コメントを投稿